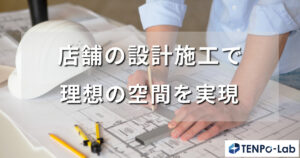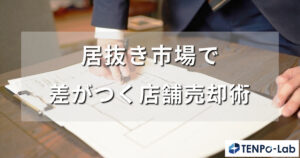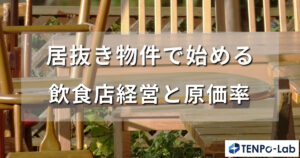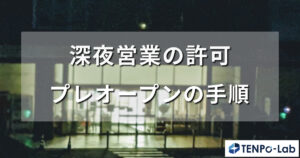建物を安全・長持ちさせるためには、「基礎配筋」が極めて重要です。鉄筋の配置や間隔、かぶり厚さなどが適切でなければ、後の構造全体に悪影響を及ぼしかねません。
本記事では、基礎配筋の基本から検査項目、工事の流れ、配筋の種類ごとの違いまで、専門的な視点で詳しく解説します。現場監理者や設計担当者だけでなく、住宅の建築を検討している方にも役立つ情報をまとめました。
基礎配筋とは何かを正確に知る

「基礎配筋」とは、建物の基礎部分に鉄筋を正確に配置する工程のことを指します。建築物の強度や耐震性に直結するため、非常に重要な工事です。一般的に木造住宅でも基礎は鉄筋コンクリートで構成され、配筋作業が不可欠です。鉄筋は設計図面に基づいて縦横に組み合わされ、所定の強度を満たすように設計されます。
コンクリートは圧縮力には強い一方で引張力には弱く、引張力に対する補強として鉄筋を使用することで、建物の安定性を保つことが可能となります。
配筋に使用される鉄筋の種類
鉄筋にはさまざまな種類がありますが、主に使用されるのは「異形鉄筋(SD)」と呼ばれる節(リブ)付きの棒鋼です。このリブによってコンクリートとの付着力が高まり、より強固な基礎がつくられます。鉄筋の太さ(D13など)は設計図によって定められており、建物の荷重や規模に応じて適切な径が選ばれます。
D10:直径10mm。軽負荷の構造に使用。
D13:直径13mm。木造基礎の標準。
D16以上:重量構造やRC造の基礎に使われる。
基礎配筋工事の具体的な流れ

基礎配筋工事の流れは次の通りです
施工図・配筋図の作成:構造設計に基づいて詳細な施工図を作成。
鉄筋加工:加工場で設計通りにカット・曲げ加工。
現場搬入と仮置き:加工済み鉄筋を搬入し、適切に配置。
組立作業:スペーサーや結束線を使って配置・結束。
人通口やスリーブの補強:必要に応じて補強筋を追加。
配筋検査:施工完了後に第三者を含む検査を実施。
コンクリート打設:合格後、速やかに打設工程へ進む。
配筋の配置とかぶり厚さの重要性
配筋の基本は「間隔」と「かぶり厚さ」です。建築基準法では、鉄筋同士の間隔(ピッチ)は300mm以下、かぶり厚さは底盤60mm以上、立上り部は40mm以上と定められています。かぶり厚さが不足すると、鉄筋が錆びやすくなり、長期的に基礎が劣化するリスクが高まります。
また、スラブ筋(底盤部の横方向筋)は施工時に下がりやすく、スペーサーブロック(ピンコロ)での支持が必要です。
鉄筋定着と継ぎ手の正しい考え方

鉄筋の長さが不足する場合、継ぎ手(定着)で接合します。この際の定着長さは、鉄筋の太さに応じて設計されています(例えばD13なら30?40cm程度が一般的)。この定着が不十分だと、引張力に耐えられず亀裂が入る原因になります。
また、梁や柱の隅角部では、30cm以上の重ね継ぎが必要とされており、特に地震時の応力が集中しやすいため補強が欠かせません。
検査時に確認すべきチェック項目
配筋検査は、コンクリート打設前に行われます。
主なチェックポイントは以下の通りです
鉄筋の本数・間隔が図面通りか
かぶり厚さの確保
波打ちやねじれの有無
定着長さの妥当性
アンカーボルト・ホールダウン金物の位置と固定
防湿シートの破損・ズレの有無
これらを第三者機関も含めて確認し、写真記録として残すことが一般的です。
ベタ基礎と布基礎の配筋の違い

配筋の方法は、基礎の種類によっても異なります。
■ベタ基礎
床一面に鉄筋を張り巡らせる方式で、建物全体の荷重を分散。湿気・シロアリ対策としても優秀です。ピッチや鉄筋量も多く、耐震性に優れた構造です。
■布基礎
立上り部分のみ鉄筋を組み、地面との接触面積が少ないため、比較的コストを抑えた工法です。ただし、耐震性や湿気対策ではベタ基礎に劣る面もあります。
いずれの基礎にしても、鉄筋の量・配筋間隔・補強筋の有無が全体の強度に直結します。
現場で見逃されやすい注意点
基礎配筋では、次のような見落としが多く発生します:
人通口の補強筋の入れ忘れ
スリーブ周辺の補強不足
スペーサーの不均一設置
アンカーボルトの曲がりや浮き
鉄筋のねじれや歪み
こうしたミスを防ぐためには、施工直後の記録写真と、複数人によるダブルチェックが有効です。
工程ごとの施工管理のポイント

基礎配筋を正しく行うには、各工程での管理が欠かせません。
施工計画書:鉄筋工事業者と内容をすり合わせ。
加工図・配筋図:実施工と差異がないか確認。
施工中の監理:寸法、位置ズレ、固定状況を目視+測定。
検査記録:検査表、黒板記載写真を残す。
特に住宅では、限られた日程の中で作業されることが多く、監理不足が後のトラブルにつながりやすい点に注意が必要です。
まとめ:基礎配筋で家の寿命が決まる
基礎配筋は、建物の安全性・耐久性に直結する非常に大切な工程です。見た目には見えない部分だからこそ、正確な施工と厳密な検査が求められます。住宅の建築や購入を検討している方も、「基礎配筋のチェック項目」について理解しておけば、現場での確認ポイントが明確になり、後悔のない住まいづくりが実現できます。
今後も安心して暮らすために、基礎こそ丁寧に。そして、見えない部分にこそ注目して工事を進めましょう。